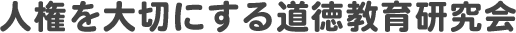中学校 道徳教科書
光村図書 きみがいちばんひかるとき
「異なり記念日」
| 内容項目 | C 主として集団や社会との関わりに関すること |
|---|---|
| 家族愛、家族生活の充実 |
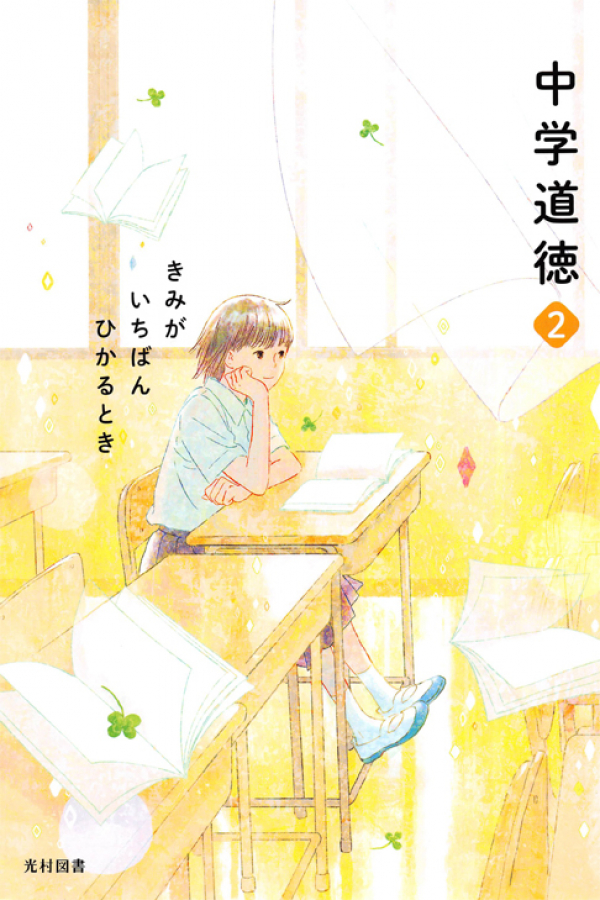
1.本教材について
▼本教材には二つのテーマがある。
▼一つは「聴覚の障害について知ろう」というテーマである。本教材の齋藤陽道(はるみち)さんとまなみさんは、言語を習得する前に音声を聞くことができなくなった「ろう者」であり、二人の子どもである樹(いつき)さんは耳が聞こえる聴者である。
▼もう一つのテーマは「家族のつながりについて考えよう」である。陽道さんの樹さんへの愛情は、あふれるばかりだが、樹さんの成長につれて、聴者である樹さんとろう者である両親との間には様々な違いが生まれる可能性がある(参考資料1,2参照)。その一つは使う言語に関することである。樹さんは成長するにつれ、音声言語である日本語を学習し、使用するようになるが、両親との間で使用する言語は日本手話である。樹さんは両親を通じてろうの世界に、また、自らの音声言語を通じて日本のマジョリティの世界にいる。つまり二つの世界で暮らすことになる。
▼「家族のつながりについて考えよう」というテーマでは、陽道さんが樹さんに「異なり記念日」と言ったことの意味を考えたい。陽道さんは樹さんの将来についてどのようなことを考えているだろうか。樹さんは、ろうのコミュニティにかかわる仕事、例えば手話通訳士になるかもしれないが、全く関係のない仕事につくかもしれない。例えば音楽家になったら、どうだろうか。自分の子どもが自分とは全く違った世界に属することになったら。このことは外国につながる子どもの家庭でも生じる問題である。日本に働きに来た外国人の家庭では、子どもは、成長するにつれ日本語が身近な言葉になり、それに反して母語を忘れていく。日本になじむのが難しい親とは、異なる世界に身を置くようになるということが起こる。
▼本教材は良い教材だが、大変難しい教材でもある。ひとつには、生徒たちが「ろう者」に関することをほとんど知らないからである。日本手話は日本語とは異なる独自の文法を持った非音声言語であること、参考資料2にあるように、ろう文化という呼ばれる独自の習慣などがあることを理解する必要がある。したがって本教材は2時間扱いで行いたい。
▼一つは「聴覚の障害について知ろう」というテーマである。本教材の齋藤陽道(はるみち)さんとまなみさんは、言語を習得する前に音声を聞くことができなくなった「ろう者」であり、二人の子どもである樹(いつき)さんは耳が聞こえる聴者である。
▼もう一つのテーマは「家族のつながりについて考えよう」である。陽道さんの樹さんへの愛情は、あふれるばかりだが、樹さんの成長につれて、聴者である樹さんとろう者である両親との間には様々な違いが生まれる可能性がある(参考資料1,2参照)。その一つは使う言語に関することである。樹さんは成長するにつれ、音声言語である日本語を学習し、使用するようになるが、両親との間で使用する言語は日本手話である。樹さんは両親を通じてろうの世界に、また、自らの音声言語を通じて日本のマジョリティの世界にいる。つまり二つの世界で暮らすことになる。
▼「家族のつながりについて考えよう」というテーマでは、陽道さんが樹さんに「異なり記念日」と言ったことの意味を考えたい。陽道さんは樹さんの将来についてどのようなことを考えているだろうか。樹さんは、ろうのコミュニティにかかわる仕事、例えば手話通訳士になるかもしれないが、全く関係のない仕事につくかもしれない。例えば音楽家になったら、どうだろうか。自分の子どもが自分とは全く違った世界に属することになったら。このことは外国につながる子どもの家庭でも生じる問題である。日本に働きに来た外国人の家庭では、子どもは、成長するにつれ日本語が身近な言葉になり、それに反して母語を忘れていく。日本になじむのが難しい親とは、異なる世界に身を置くようになるということが起こる。
▼本教材は良い教材だが、大変難しい教材でもある。ひとつには、生徒たちが「ろう者」に関することをほとんど知らないからである。日本手話は日本語とは異なる独自の文法を持った非音声言語であること、参考資料2にあるように、ろう文化という呼ばれる独自の習慣などがあることを理解する必要がある。したがって本教材は2時間扱いで行いたい。
2.本教材を扱う際に、特に注意すべきだと考えたこと
▼1限目では「聴覚の障害について知ろう」というテーマを中心に扱う。まず手話などについての知識を理解する必要があり、それを踏まえて陽道さんの家族について考えてみたい。
▼2限目の指導過程では、陽道さんは樹さんに「ぼくらは異なる存在だ」と告げる必要があると思っていることに気づきたい。そのうえで陽道さんと樹さんはどのような親子になっていくのかを考えたい。 さらに翻って考えれば、親子は皆20歳から30歳くらいの年齢差があり、どのような親子であろうと価値観のずれがあって当然である。陽道さんたちの家族のことを考えることで生徒が自分たちの家族の問題を考えることにもつなげたい。
▼2限目の指導過程では、陽道さんは樹さんに「ぼくらは異なる存在だ」と告げる必要があると思っていることに気づきたい。そのうえで陽道さんと樹さんはどのような親子になっていくのかを考えたい。 さらに翻って考えれば、親子は皆20歳から30歳くらいの年齢差があり、どのような親子であろうと価値観のずれがあって当然である。陽道さんたちの家族のことを考えることで生徒が自分たちの家族の問題を考えることにもつなげたい。
3.指導過程
ーー指導案と参考資料(補足資料など)はPDFをご覧くださいーー
ーー指導案と参考資料(補足資料など)はPDFをご覧くださいーー