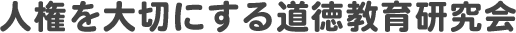中学校 道徳教科書
「領民を愛した名君 上杉鷹山」
| 内容項目 | A.主として自分自身に関すること |
|---|---|
| 自主、自律、自由と責任 |

Gakkenは、「領民を愛した名君 上杉鷹山」という表題で、上杉鷹山を教科書で取り上げている。本教材が道徳の教材として適切なものかどうかを検討したい。
《ケネディ米大統領が「日本で最も尊敬する政治家はだれか」という問いに「上杉鷹山」の名をあげたのは事実か》
▼Gakkenの教科書では、冒頭にケネディ米大統領が「日本で最も尊敬する政治家はだれか」という問いに「上杉鷹山」の名をあげたと答えているが、加来耕三はどこにそのような史実があるのか、「歴史を安直に創ってはいけない」と書いている(①参照)。ネット上でも諸説紛々である。ちなみに「米沢 上杉観光」というWEBページにはケネディだけでなく、クリントン元大統領も鷹山を尊敬していたと書かれている。
▼ケネディの発言の真偽は置くとしても、大名は政治家なのか。政治家というのは職業であり、その言葉は近代のものではないかなど違和感のある部分だが、少なくとも教科書があっさり断定的に書いているほど根拠のあることではないようだ。
《イメージで描いた挿絵の根拠はあるのか》
▼教科書p98に書かれている挿絵について、教科書を作成した学研に「挿絵の人物は鷹山を想定しているのか、あるいはほかの人物か。またその根拠はあるか(鷹山が実際に指揮していたと思われる根拠)」を問い合わせたところ次のような回答があった。
「『挿絵の人物は鷹山を想定している』、『農村を復興させようと指揮をとっている鷹山、不満を募らせた家臣というイメージ』で、本文と合わせて米沢市上杉博物館学芸員の方に確認してもらっている」、とのことである。事実を根拠にしてではなく、教科書作成者のイメージを挿絵にしているということのようだ。
《鷹山自身も鍬を持ち農業をしたのか》
▼教科書p99には「鷹山自身も鍬を持ち、農業の大切さ、農業を盛んにしたいという思いを伝えようとしました」とあり、まるで鷹山自身が農作業をしたかのように書かれているが、誤った理解をさせる表現である。「籍田の礼」のことを指しているのであろうが、籍田の礼とは儀式である。鷹山をはじめ、役人が参列し、鷹山は3鍬を打つ、という儀礼であり、中国古代の周に倣ったものだそうである(②参照)。
《名君録に描かれた鷹山像は事実に基づいているのか、それともあるべき名君像に基づいているのか》
▼鷹山を名君として有名にしたのは『翹楚編』と呼ばれる名君録で、鷹山の下で改革を担った執政、莅戸善政が執筆したものである。小関悠一郎は著書(③)で、「鷹山を含めた『名君』が改革にどのような役割を果たしたのかは、自明のことではない」と述べている。また、『翹楚編』などの名君録は「君主個人を顕彰する意図が色濃く、記述の事実性を確定するにも困難が伴う」とも述べている。小関は、伝えられている鷹山の言行が事実かどうか、確定するのは困難だから、莅戸がなぜかかる名君録を書いたのか、そこでは鷹山をどのように描いているのか、米沢藩の改革とどのような関係があるのか、を考えてみたいと述べている。
▼小川和也は、『牧民の思想』(⑤)で、「『名君録』とは、実在の将軍、大名を理想化して描いたもので、虚実の入り混じった物語性をもつ記録である」、「名君録は、あるべき君主像を描き、そこに『仁政』思想を仮託する」、「近世日本においては『史上の人物に託して、政治の評論を行う』政治的伝統・習慣が存在した」と述べている。
▼つまり、名君録というのは事実をもとにしながらも為政者のあるべき姿にあわせて虚構、誇張、作為が込められており、どこまでが事実なのか、はっきりしないのである。名君録に基づいて書かれている上杉鷹山についての教科書の記述にも、虚構、誇張、作為が含まれていると考えられる。
(なお名君録の成り立ち等については④を参照)
《近世国家の正当性―幕藩制イデオロギー》
▼家康は、権力を掌握して将軍になると、民政に関する「仕置き」を出し、百姓に対する領主、代官の苛政を禁止し、民衆の生命の維持を宣言した(⑤参照)。徳川幕府の元での平和とは、民百姓が生命の危機から脱し、安んじて暮らせる世(百姓成り立ち)を意味していた。近世国家はこうした理念、あるいは幻想を掲げながら、民衆に統治支配の正当性を認めさせていく。深谷克己、宮沢誠一はこれを幕藩制イデオロギーだとし、このイデオロギーの中心は「委任」と「お救い」だとする。「委任」とは、「天道」が将軍、大名へと下降しつつ統治を委任するという意味である。「委任」と「お救い」を結びつけるのは「治国安民」=仁政思想である。(なお、幕藩制イデオロギーについては⑥を参照)
▼仁政思想は近世政治文化の常識となったが、この常識を人格として表現したのが「名君」であり、その具体的な有り様を描いたのが名君録である。名君は大名家、将軍家に必ず1人はおり、名君録は定義にもよるが、数千にのぼるという(⑤参照)。
《「藩主は国の父母」というのは鷹山が本当に言ったことか》
▼教科書p96の表題「領民を愛した名君」p97の鷹山が詠んだと言われる「受け継ぎて国の司の身となれば忘るまじきは民の父母」は近世政治文化の基本となった仁政思想そのものを表している。これらの仁政思想は吉宗の時代には、統治者にとっては「たてまえとして」常識になっていたと考えられる。つまり、「藩主は国の父母」と鷹山が言ったのか、鷹山が名君ならば、そう言うはずだと名君録の著者が思ったのか、今となってはわからない。
▼本教材は上杉鷹山の名君録をもとに作られている。すでに述べたように名君録には、為政者のあるべき姿に合わせて虚構、誇張、作為が、事実とともに込められ、塗りこめられている材料の中でどれが事実でどれが事実でないか、区別をつけるのが困難なのである(③参照)。小関悠一郎は鷹山と同じく「名君」と言われた細川重賢について、次のように述べている。「重賢が残した日記などをはじめ当時の記録(藩政資料)には、政治の話題は一切なく、重賢が熊本藩政をどう指導したか、確実な資料からは判然としない」という」(③p.11)。
▼これまで本会ホームページでは、不十分、不適切な教材であってもそれを補う教材を工夫するなどして指導案を作成してきた。それは現場の先生方にとっては、たとえ不十分な教材であっても、授業をしないという選択肢は取りにくいだろうと思ったからである。しかし本教材は部分的に不適切な箇所があるからということではなく、全体として不適切なのである。部分的な修正や補足は無意味だと考える。どれが事実で、どれが事実でないかわからない偉人伝を道徳教材とするべきではないので、この教材を用いての授業はすべきではないという意味で、指導案も作成していない。
① 『異端の改革者 上杉鷹山』加来耕三 集英社 2001年
② 「米沢藩の財政改革と上杉鷹山」大矢野栄次 久留米大学経済社会研究vol58第1、2合併号2018年
③ 『上杉鷹山』小関悠一郎 岩波書店 2021年
④ 若尾政希「享保~天明期の社会と文化」大石学編『日本の時代史16』所収 2003年
⑤ 『牧民の思想』小川和也 平凡社 2008年
⑥ 岩田浩太郎「正当性と世界像」『新しい近世史NO5』所収 新人物往来社1996年
《参考資料》
福澤諭吉の「仁政思想」批判(「学問のすすめ」より、⑤の「牧民の思想」から再引用)
アジア諸国では国君(各藩の殿様)のことを民の父母と言い人民のことを臣子、または赤子と言い、政府の仕事を牧民の職と呼んでいた。「牧」という字は獣を養うという意味だから、人民にとっては失礼な言い方であろう。
しかし、人民を獣のように、子どものように扱うといっても悪気はないのだ。聡明で素晴らしい殿様が、私心のないまっすぐな心を人民にも及ぼし、情愛豊かに飢饉の時には米を与え、火事の際には見舞金を渡し、いつも救いの手を差し伸べて南風が薫るようで、人民が従うのは草がなびくようで、全く極楽のようだ。
しかし、よく考えてみれば政府と人民は血縁があるわけではない。他人の付き合いである。他人と他人の付き合いでは「情愛」を基にするわけにはいかない。規則や約束をつくって互いにこれを守ったり守らなかったりするうちに丸く収まるのだ。ここにこそ国法ができた理由がある。
現実には神でもない殿様が、無理を重ねて「御恩」を施そうとしても、「御恩」は迷惑となり「仁政」は悪法になってしまうというのが現実なのだ。