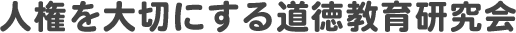小学校 道徳教科書
「二わのことり」(A案)
| 内容項目 |
B主として人との関わりに関すること C主として集団や社会との関わりに関すること |
|---|---|
|
友情、信頼 公正、公平、社会正義 |

(本案では、教材に登場する鳥たちの名を全てカタカナで表記する)
(1)教材の内容について
▼クラスのみんなは、ヤマガラの誕生日の招待状を受け取った。しかしその日は、ウグイスの家でおこなう音楽の練習日と重なっていた。どちらを選ぶとなった時、みんなはウグイスの家に行くことを選んだ。ウグイスは明るいきれいなところに住み、ヤマガラの家は山奥のさびしいところにある。ミソサザイは、どちらに行こうか迷っていたが、みんなと一緒にウグイスの家に行く。しかし、ミソサザイは、ヤマガラのことが気になってちっとも楽しくない。とうとうミソサザイはこっそり抜け出して、自分だけ、ヤマガラのもとに行く。ヤマガラは誰も来てくれないと失望していたところに、ミソサザイが来てくれたので喜び、ミソサザイの思いやりの心に感動するのである。
▼感動的な話で、低学年の子に「やさしさ」を学ばせるのに適した教材かもしれない。だからこの教材は定番教材として、小学校の全ての教科書に採用され続けているのだと思われる。
▼また、道徳の書籍や雑誌、ネットにupされている指導案でも、そのほとんどが、つまるところ「みなさんも、ミソサザイさんのように、やさしいこころをもとうね」ということに帰結しているように思える。しかし果たしてそれでよいのだろうか?
▼低学年の教材には動物たちの世界の話を用いることが多い。低学年の子が楽しく教材の世界に入っていくための方法であることは言うまでもない。ただ、その動物の世界のお話が現実の子どもたちの世界とあまりに乖離してしまっては、道徳の教材にする意味がない。もし、この教材を使っての学習の帰結が「やさしさの大切さ」になるならば、この教材の示す世界は、子どもたちが生活する現実の社会とは乖離していると言わざるを得ない。
▼もし実際に、ミソサザイがこの教材のような行動をした場合、現実的には厳しい事態が起こってくると容易に想像できる。ウグイスの家をこっそり抜け出した後、ウグイスたちのなかでは騒ぎになって、批判が飛び交うであろう。次の日学校に行くと二人はみんなの冷たい視線を浴びることになるだろう。
つまり、この教材のような行動をミソサザイがとった場合、問題の解決どころか、クラスのみんなとの関係性をより悪化させることになってしまうことも考えられる。
(2)この教材が示している解決すべき課題とは
▼1年生の子どもたちにとって「社会」とは、「学校」であり「クラス」である。この教材もクラス内の問題を扱っており、子どもたちは教材を通してクラスという自分にとっての「社会の問題」を考えることになる。
▼さて、この教材が示している解決すべき問題とは何だろうか。ミソサザイのような「やさしさ」「思いやり」をほかの鳥たちが持たないから、ヤマガラが誕生日に悲しい思いをしたことなのか。
否である。
▼ヤマガラからの誕生会招待状をみんなが受け取ったにもかかわらず、みんなは当然のようにウグイスの家に行ってしまう。誕生会と練習日が重なったことを「困ったなぁ…」「どうしよう…」とみんなが相談したり、ヤマガラ本人や、主催者と思われるウグイスとも相談したりすることは一切なかった。
▼つまり、ヤマガラはこのクラスで排除されている(いじめられている)のである。この教材はその状況を示している。どの教科書も多少の違いはあるが「ヤマガラのうちは、山おくのとてもさびしいところにあります」というネガティブな表現もそれを暗示するものである。
したがって、このクラスの解決すべき問題は、ヤマガラがクラスのみんなに排除されていることではないだろうか。
(3)ミソサザイの行動について
▼さびしい、つらい思いをしている人にまず必要なのは誰かが寄り添うことである。たった一人でも「あなたのことを大事に思っている」と寄り添ってくれる友人がいれば、人は救われる。
▼ミソサザイはみんなと一緒にウグイスの家に行ってしまったが、勇気を振り絞ってヤマガラのもとへ飛んでいく。ヤマガラはミソサザイが来てくれたことで目に涙を浮かべて喜ぶ。まさに、たった一人でも寄り添ってくれたことで救われるのである。そのミソサザイの“やさしさ”と勇気ある行動は、評価すべきであるし、子どもたちにも是非共感してもらいたいところである。
▼しかし、その行動だけでは問題は解決しない。ミソサザイの“やさしさ”あふれる行動は、問題をより複雑なものにする可能性すら含んでいる。そういう意味では、ミソサザイの選択した行動は、ベストの行動ではなかったと言える。それは、ミソサザイが自分のクラスの問題(ヤマガラに対する排除)を十分に意識できていなかったせいかもしれない。
(4)子どもたちに考えさせたいこと
▼前述したように、1年生の子にとって、学校、クラスは「社会」である。そして、この教材は、クラスの問題…つまり「いじめ」を内包しているのであるから、子どもたちにもそれに気づかせ、その問題を解決する方向で考えさせたい。ミソサザイが発揮した「勇気」「やさしさ」「行動力」を是非問題解決の方向に向けることを考えさせたい。
▼子どもの「社会」で起こっている「差別」「いじめ」に目をつぶって、個人の“やさしさ”の問題に帰してしまうのは、決して“人権的”とは言えない。ヤマガラがクラスでいじめられていても、もしもそのいじめの背景に部落差別などの人権課題や差別があったとしても、そういった“差別”に目をつぶり、「ミソサザイのようにやさしくしようね」で終わらせてしまうと、厳しい見方をすれば「反人権的」とも言えるのではないだろうか。
▼「社会の問題を見抜き、それをどのように解決していくかを考えること」…これは人権の視点の学習での大切な要素である。1年生であっても、1年生なりに考えさせていきたい。それができれば、この教材は優れた人権学習の教材となるだろう。
▼前述したように、この教材で子どもたちに共感してもらいたいこと、考えてもらいたいことは2つある。①一つはミソサザイが一人ぼっちのヤマガラに寄り添った“やさしさ”あふれる行動に共感してもらいたいこと。②もう一つは、ヤマガラがクラスのみんなに排除されていることを理解したうえで、この状況を改善するための、別の方法はなかったのかを考えることである。
▼そう考えると、2時間計画にした方がよいだろう。①と②を1時間ずつ行う方が、1年生の児童には適切かと思われる。
▼第1時は、一気に最後まで読んで、ミソサザイだけでも来てくれたことをヤマガラが喜び、わずかながらでも孤独が癒されたことを、子どもたちにもやまがらの気持ちになって、まず素直に喜んでもらいたいと考える。そして、ヤマガラが涙を流して喜んでいるのを見て、ミソサザイもヤマガラの孤独の深さを感じ取り、はじめは迷ったけれど、ヤマガラの家に来て本当に良かったと思う。そういったことにも素直に共感してもらいたい。
▼第2時は、次の日から始まり、原因と解決策を探っていきたい。
次の日に、ウグイスも含む他の小鳥たちに会ったら、二羽がどんなことになるかは1年生の子どもたちでも容易に想像できるだろう。「一斉に非難の目で見られるのではないか」とか「裏切り者だと言われるのではないか」とか、「今度はミソサザイがのけ者にされるのではないか」などなど。つまり、これまではのけ者はヤマガラだけだったのが、さらにミソサザイものけ者になってしまう可能性が出てくることに気が付くだろう。
▼なぜミソサザイはそんな仕打ちを受けるかも知れないのだろう…。それは「みんなに知らせず、勝手にヤマガラのもとに行ったから」だけが原因だろうか。
ここで遡って考えてみると、ヤマガラがみんなから排除されている状況が改めてはっきり見えてくる。
▼掘り下げるべき核心問題は、1年に一度しかないヤマガラの誕生日を優先すべきだと考えなかった小鳥たちの集団にある。練習はまた別の日でもできるけれど、誕生日はその日しかない大事な日であり、ヤマガラがせっかくお祝いの会を開くから来てほしいと招待しているのに、無視していいのかとという問題である。ヤマガラは差別され、対等な仲間とは考えられていない存在だったということである。集団の中にいながら実質上いないかのように扱われているヤマガラ。そんなヤマガラに味方したら、ミソサザイは無視されることにとどまらず、周りを敵にまわしかねないことを起こしたのである。そこに気づかせるように考えさせたり、話し合わせたりする必要がある。
▼1年生なので、深めるといっても難しいかもしれない。しかし、1年生の子どもは表現の言葉は少ないけれども、直観力も想像力もある。自分の誕生会に誰も来てくれなかったらどんなに悲しいか十分わかるし、無視する側になってはいけないこともわかる。この小鳥たちに問題があることも理解できるだろう。だから、きちんと問題を理解させたうえで、「では、みそさざいはどうしたら良かったのだろうか」と解決策を考えさせたい。(ただ、補助発問はいくつか準備しておく必要があるだろう)
▼このように考えていくと、ミソサザイはウグイスたちのもとを抜け出すのではなく、事情を話し、ウグイスや他の鳥たちも誘って、ヤマガラのところに行くことを選択肢にすることも気づけるのではないだろうか。そういった発想が、ウグイスたちも“悪者”にしないで、みんなで気持ちよくやまがらののもとに行け、みんなが仲間になっていく方向に踏み出せることに気付かせたい。
《子どもたちに考えて欲しいこと》
ヤマガラがクラスのみんなから排除されている状況をふまえ、誕生会と練習日が重なった件で、ミソサザイがどのような行動をすれば、このクラスの問題を改善させていけるか考える。